明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼,造船,石炭産業-1

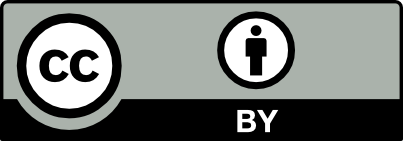
明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業は、山口・福岡・佐賀・長崎・熊本・鹿児島・岩手・静岡 の8県に点在します。
西洋から伝わった技術と、日本の伝統文化を融合させ、幕末から明治にかけて急速な発展を遂げた炭鉱、鉄鋼業、造船業に関する文化遺産です。
稼働遺産(現在でも稼働中の状態のもの)を含む世界遺産としては、日本初となりました。
構成資産が、8県23件にのぼるので、全4回に分けて紹介させていただきます。
エリア1-萩(山口県)
萩反射炉


日本に現存する2基の反射炉のうちのひとつ。
欧米列強に対抗するために、長州藩は海防強化のための鉄製大砲製造の必要性に迫られました。
そこで、先んじて反射炉の操業を始めていた佐賀藩から技術を導入し、1,856年より操業が開始されましたが、規模が小さいため実用炉ではなく実験路であったと考えられています。
恵美須ヶ鼻造船所跡


黒船来航による危機感から、幕府は大型船建造の禁を1,853年に解きました。
長州藩は、幕府の要請と桂小五郎(木戸孝允)の意見書を受け、幕府がロシア式造船を行っていた造船所に藩士を派遣し、帰国した彼らによって造船所が建設されました。
そこで初期にはロシア式造船。後期にはオランダ式(バーク船)が建造されました。
大板山たたら製鉄遺跡


在来の”たたら製鉄”の技術を用いて江戸時代中期より操業し、江戸時代後期(幕末)には、洋式軍艦の建造に欠かせない鉄の供給を行いました。
炉、天秤ふいごなどの遺構が発掘されています。
萩城下町

幕末から明治時代にかけて、日本の近代国家形成を手動した雄藩のひとつ、長州藩の中心拠点です。
1,604年に毛利氏の戸城として萩城が建設され、城下町が形成されました。
武家屋敷や商家が連なる「萩城城下町」は国の史跡に指定されており、重臣の屋敷が並ぶ「堀内地区」は国の重要伝統的建造物群保存地区となっています。
松下村塾

長州藩校【明倫館】の師範を務めた吉田松陰が講義した私塾です。
桂小五郎(木戸孝允)・高杉晋作・伊藤博文・山縣有朋・久坂玄瑞・吉田稔麿など、幕末から明治にかけて活躍した人々を多数輩出し、その中には日本の近代化・産業化に貢献した人材も含まれます。

コメントを残す